

この項目は難しいのですが、大学で学んだELSI関連を記載していく予定です
修辞学とは
修辞学とは、自身の考えや主張を伝えるための手法となる技術・学問のことです。
踏み込んだ言い方をすると、作家や話者が特定の状況・聴衆に対して
情報を与え、説得し、あるいは動機づけるために利用する技法を研究すること
を目的としています
弁論術 / コミュニケーション学 / プレゼンテーション術 /
クリティカルシンキング / アカデミックライティング
古代ギリシアのソクラテスは、弁論術は慣れによって得られる一種の道具ととらえ、
弟子のアリストテレスは真実・真理を探究する分野であると捉えていました。
古代ギリシアから19世紀後半まで、古典修辞学は西洋の教育において
中心的な役割を果たしていました。
しかし実は、古典修辞学は、欧州及び米国では衰退しています。
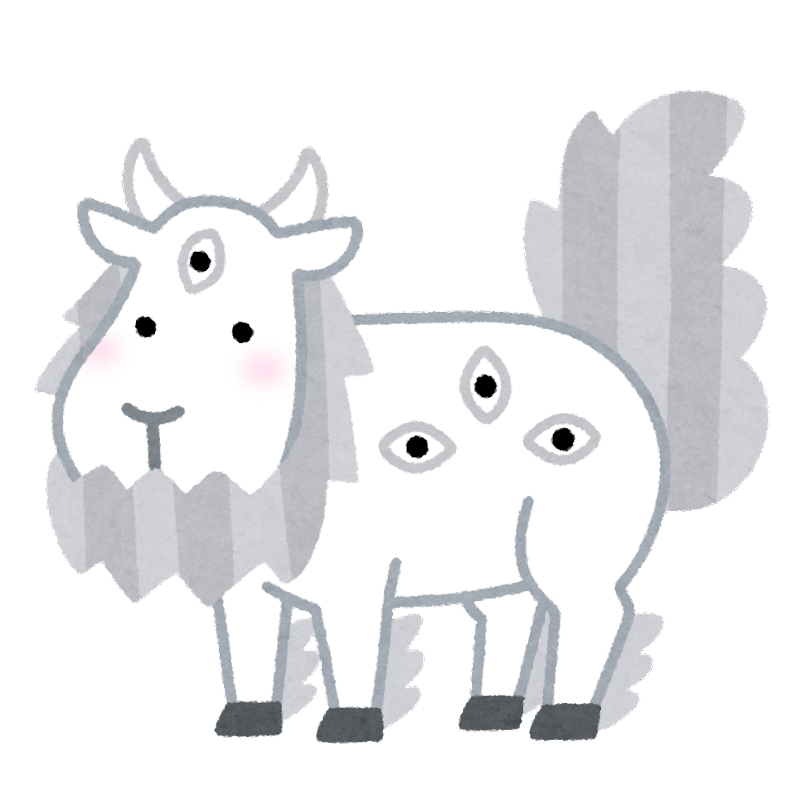
日本へ本格的に入ったのは19世紀後半の明治時代とさされておる。
その後、日本独自の修辞学が急速に発展していったのじゃ。

そのあたりのこともいつかそのうち…
ELSIとは
ELSI(米国)およびELSA(欧州)は、倫理、法、社会的影響、または社会的側面の頭字語です。
ethical, legal and social implications (ELSI)or
social aspects (ELSA)
特にゲノムやナノテクノロジーといった新興科学の倫理的、法的、社会的影響(ELSI)または
社会的側面(ELSA)を予測して対処する、研究活動を指しています。
ELSIが考案されたきっかけ
それは、1988年、ジェームズ・ワトソンがヒトゲノム計画(HGP)の責任者に
任命されたことを発表する記者会見の時でした。
突如、「ゲノミクスの倫理的・社会的影響には特別な取り組みが必要であり、
NIH*が直接資金を提供すべき」 だと宣言したのです。
*USAにある国立衛生研究所(National Institutes of Health : NIH)
ELSIには、新規科学技術を研究開発し、社会実装する際に生じうる技術的課題以外の
あらゆる課題を含みます。

講義受けながら、研究者は只でさえ技術的課題と資金獲得に苦しんでいるのに
更に面倒なことも考えなきゃいけないなんて、疲れるなーと思ってました
目指す人が減るわけですよ
例を挙げるのも難しいのですが、例えば、AI(人工知能)の発展には倫理原則の課題が付きまといます。
また、医師側が患者権利を侵害せず、治療や研究を進めるための国際的ルールである
「インフォームド・コンセント」にも、著しい医学の発展による問題が浮かび上がってきました。
ELSIの課題は、専門家だけが考えていくのではなく、以下がカギとなります。
- 如何に多くの人を巻き込み、多様性のある議論を発展させられるのか
- 議論の発展によって、社会を変えていけるのか
つまり、多くの人と議論をしていくための手法として修辞学が必要なことから、
ELSIは修辞学に含まれる、との判断です。
参考文献
日本の展望―学術からの提言 2010 21世紀の教養と教養教育, 日本学術会議 日本の展望委員会 知の創造分科会
「中川千咲 日本美術年鑑所載物故者記事」(東京文化財研究所)🔗

